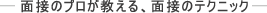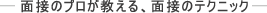「私は、同期入社では、トップの評価を得ています。」と自信満々に話をする人がいます。あるいは、これに近い話をする人がいます。「同期でトップ、あるいは高い評価」は、採用側にとって魅力的なポイントではあるのですが・・・。
採用は、相対評価です。当然、応募者と採用する数に開きがあります。魅力ある企業の場合、競争相手というものが、多く存在します。
自分よりも、優秀な人が、応募にきていれば、そちらを採用する可能性が高くなるでしょう・・・。
「優秀か。優秀でないか。」という評価は、実は、応募者間の相対評価というよりも、その会社で働く同世代との相対評価によるところが大きいです。
極端な話、「今いる社員をクビにしてでも、応募者と入れ替えたいかどうか。」になります。
企業ブランド
それでは、人事マンが、自社の社員と比較するときの基準について触れておきます。
応募者の属性を4つのタイプに別けることができます。
(上位・下位というのは、企業が持つブランドイメージです。)
A. 同業他社で、上位企業に勤務する(勤務していた)応募者
B. 同業他社で、下位企業に 〃
C. 他業界で、上位企業に 〃
D. 他業界で、下位企業に 〃
例えば、A.の応募者で、冒頭の「同期で、トップの評価でした。」という話は、「凄い」と評価するよりも、「何で?・・・・当社なの?」と疑問の方が先にきます。
C.の場合も、同様の思いが、発生するでしょう。B.C.は、「凄い」という評価よりも、「頑張ったのね」みたいな感じ方になってくるでしょう。
ここで問題にしたいのは、いずれの場合も、「トップの評価」という言葉が持つ危険性です。
上位だろうが下位だろうが、「同期の中で、評価は下の方でした。」という人を、採用したいと思わないでしょうけど。
「トップの評価」というのが、企業のランキングを想起させる言葉であり、人事の『負けん気』を煽る危険性があります。
5番目の実力
例えば、ある学校で、「私は、成績がトップでした。」という言葉は、偏差値が高い学校であればあるほど、聞き手は、嫌な気持ちを持つかもしれないということです。
人によっては、「トップだったかもしれないけれど、全部のテストあるいは、全教科のテストが、トップだったわけではないだろう・・・」などと反感を買うかもしれません。
そこで、例えば、「成績は、5番くらいでしたね。」という言葉は、妙に、リアリティがあり、「トップになったこともあるのでしょうね。・・・・」と聞き手が、勝手に想像したりするものです。
|