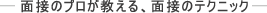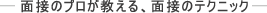|
『疑わしきは、上にあげず』というケースが起こります。上司に、この人は、「どんな人物?」とか聞かれたときに、何と答えよう。「うーん、上司に上手くコメントできないのは、嫌だから・・・・・、うーん、アウトにしちゃおう・・・・」といった信じられない行動をとる人事マンもゼロではありません。
『一般的に考えられている面接』は、
|
|
応募者
|
|
面接官
|
|
A
|
一
|
対
|
一
|
|
B
|
一
|
対
|
多
|
|
C
|
多
|
対
|
一
|
|
D
|
多
|
対
|
多
|
の4種類です。
「C」「D」は、グループ面接といわれるものです。
一人でも評価するのは難しいのに、一度に複数の方を理解しろというのは、・・・。ある意味、応募者を軽んじた面接と言えるかもしれません。
「A」「C」の面接官が一人の場合は、前述した、面接官が緊張する危険性がありますが、
「B」「D」の面接官が複数の場合は、「疑わしきは上にあげない。」の心理が働きやすいのです。
「B」「D」の複数の面接官で面接を行なう場合の組み合わせとして、次のようなものが考えられます。
|
1次面接
|
人事マンと現場マネージャー(配属予定先)のセット
|
|
2次面接
|
人事マンと人事部長のセット
|
|
最終面接
|
人事部長と役員のセット
|
いずれの場合も、応募者を面接すると同時に、同席する他の面接官の視線を意識することになります。面接が終了した時点で、『擦り合わせ』という、各面接官が応募者に対する評価を持ち寄って、合否を決定する場面があります。人事マンは、自分自身の評価の正当性を、『誉める』ことよりむしろ、『厳しいコメント』に頼ってしまう傾向が多いようです。プラス面より、マイナス面のコメントのほうが、一見正しい評価のように聞こえるからです。他人のことを厳しく言う人を、「人を見抜くのが得意」なんていう誤った評価している人もいるのでは、ないでしょうか。企業としても、効率化・人件費削減などの問題で、安易に従業員数を増やすことができません。○コメントより×コメントが受け入れ易いものです。
|